2017年02月03日
お寺と住宅では畳の敷き方が違うーその訳は?日本人の感性に脱帽
こんにちは☆
さぬき市谷野設計の谷野です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
昨日は、大阪に勉強会に行っていました。
母の誕生日でもあったので、帰りに花を買って帰りプレゼントしたら、とても喜んでくれて、ホッコリ(*‘ω‘ *)
前回は、古くて新しい畳の歴史について書きました。
今日は、畳の敷き方についてご紹介します。
「畳敷様(たたみじきよう)」という言葉をご存知ですか?
畳の敷き方にも様式があるんです。
現在のようにフローリングが普及する前、畳の和室がほとんどだった頃には、一般の家庭でも畳を敷き替える風習がありました。
「畳敷様」とは、畳を敷き替える時の社会的な慣習のことです。
法隆寺の工匠(こうしょう)・平政隆(たいらまさたか)が記した「『愚子見記(ぐしけんき)』という建築に関わる技術書に使い分けの仕方が記されています。
この「畳敷様」という慣習が出来たのは、江戸時代。
婚礼や葬儀も家で行うことが普通だったので、祝い事と不幸の時を区別する際に、畳の敷き方を変えていました。
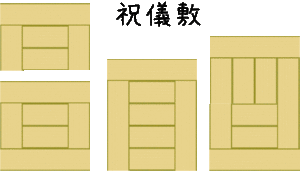

婚礼の時は「祝儀式(しゅうぎじき)」、不幸の時は「不祝儀敷(ぶしゅうぎじき)」と使い分けていたんです。
じゃあ、普段はどうしていたの?というと、
江戸時代に町屋や庄屋に畳が広まったといっても、まだ畳は貴重品。
町屋や庄屋では、畳は常に敷いておくものではなく、普段は重ねて置いておき、状況に合わせて使用していました。
武家屋敷など身分の高い者の家では祝儀敷で敷かれていたと思われます。
現在は、畳を敷き替える風習はなくなりましたが、名残はあります。
現在一般家庭で見られる敷き方は「祝儀敷」、お寺の本堂や大きい和室などでは「不祝儀敷」が用いられます。
更に、茶道から生まれた敷き方もあって、伝統から培った知識を基に、職人は畳の敷き方によって呼び分けています。
畳の1枚が枕のように敷いてある敷き方を「枕敷(まくらじき)」

枕のように配置された1枚を「枕畳」と呼びます。
茶道から生まれた敷き方で、祝儀敷と同じように畳の角が合わないように敷いたものを「回し敷(まわしじき)」とか「追い回し敷き」と呼びます。

書院造などで敷かれる敷き方で、明治以降に不祝儀敷きとされた「四居敷(よついじき)」。
「芋敷き(いもじき)」とも呼ばれます。
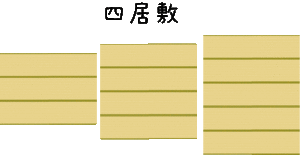
ズレが起きにくい敷き方です。
縁側などに用いられる敷き方で、畳の縁を接して並べる敷き方を「縁敷(えんじき)」
歩きやすいように考えられた敷き方です。
どれにも属さないものを「乱敷(らんじき)」と呼びます。
自由な発想で畳を楽しむもので、最近のモダンな和室に多く用いられます。

この他にも、床(とこ)の前は、上座の畳縁を踏まないように床(とこ)と並行に敷く。
入口になる部分は、歩きやすいように入り口と並行に敷く。
といった畳の決まり事があります。
畳の敷き方にまで、生活の場面に合わせて気を配っていたなんて(´▽`)☆
日本人って素敵だなぁ~と感じます☆
次回は、勉強会で耐震診断と補助金の話題が出たので、耐震性に対しての想いを書きたいと思います。
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市谷野設計の谷野です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
昨日は、大阪に勉強会に行っていました。
母の誕生日でもあったので、帰りに花を買って帰りプレゼントしたら、とても喜んでくれて、ホッコリ(*‘ω‘ *)
前回は、古くて新しい畳の歴史について書きました。
今日は、畳の敷き方についてご紹介します。
「畳敷様(たたみじきよう)」という言葉をご存知ですか?
畳の敷き方にも様式があるんです。
現在のようにフローリングが普及する前、畳の和室がほとんどだった頃には、一般の家庭でも畳を敷き替える風習がありました。
「畳敷様」とは、畳を敷き替える時の社会的な慣習のことです。
法隆寺の工匠(こうしょう)・平政隆(たいらまさたか)が記した「『愚子見記(ぐしけんき)』という建築に関わる技術書に使い分けの仕方が記されています。
この「畳敷様」という慣習が出来たのは、江戸時代。
婚礼や葬儀も家で行うことが普通だったので、祝い事と不幸の時を区別する際に、畳の敷き方を変えていました。
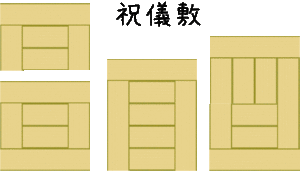

婚礼の時は「祝儀式(しゅうぎじき)」、不幸の時は「不祝儀敷(ぶしゅうぎじき)」と使い分けていたんです。
じゃあ、普段はどうしていたの?というと、
江戸時代に町屋や庄屋に畳が広まったといっても、まだ畳は貴重品。
町屋や庄屋では、畳は常に敷いておくものではなく、普段は重ねて置いておき、状況に合わせて使用していました。
武家屋敷など身分の高い者の家では祝儀敷で敷かれていたと思われます。
現在は、畳を敷き替える風習はなくなりましたが、名残はあります。
現在一般家庭で見られる敷き方は「祝儀敷」、お寺の本堂や大きい和室などでは「不祝儀敷」が用いられます。
更に、茶道から生まれた敷き方もあって、伝統から培った知識を基に、職人は畳の敷き方によって呼び分けています。
畳の1枚が枕のように敷いてある敷き方を「枕敷(まくらじき)」

枕のように配置された1枚を「枕畳」と呼びます。
茶道から生まれた敷き方で、祝儀敷と同じように畳の角が合わないように敷いたものを「回し敷(まわしじき)」とか「追い回し敷き」と呼びます。

書院造などで敷かれる敷き方で、明治以降に不祝儀敷きとされた「四居敷(よついじき)」。
「芋敷き(いもじき)」とも呼ばれます。
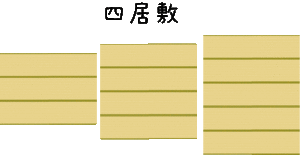
ズレが起きにくい敷き方です。
縁側などに用いられる敷き方で、畳の縁を接して並べる敷き方を「縁敷(えんじき)」
歩きやすいように考えられた敷き方です。
どれにも属さないものを「乱敷(らんじき)」と呼びます。
自由な発想で畳を楽しむもので、最近のモダンな和室に多く用いられます。

この他にも、床(とこ)の前は、上座の畳縁を踏まないように床(とこ)と並行に敷く。
入口になる部分は、歩きやすいように入り口と並行に敷く。
といった畳の決まり事があります。
畳の敷き方にまで、生活の場面に合わせて気を配っていたなんて(´▽`)☆
日本人って素敵だなぁ~と感じます☆
次回は、勉強会で耐震診断と補助金の話題が出たので、耐震性に対しての想いを書きたいと思います。
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp






