2016年02月08日
大阪城多聞櫓(たもんやぐら)
こんにちは☆
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
大阪城で内部特別公開されている多聞櫓(たもんやぐら)、千貫櫓(せんがんやぐら)、焔硝蔵(えんしょうぐら)に先週末行ってきました。
今回は、多聞櫓(たもんやぐら)をご紹介します☆
公開されているのは、大手口の多聞櫓。
大阪城の4つある出入り口の一つで、表玄関に当たる「大手口」を入り、桝形(ますがた)という防衛のための四角く開けた場所を囲むように建っています。
侵入していた敵を迎え撃つ役割を持った建物です。
他の桝形の場所にもあったのですが、現在は大手口の多聞櫓だけが残っています。
徳川幕府の大阪城再築により建造されましたが、その後落雷で焼失。現在の多聞櫓は幕末に再建され、昭和44年に解体修理されたものです。
多聞とは、石垣の上に建てられた長屋のことで、この大手口多聞櫓は渡櫓と続櫓からなっています。
城壁としての機能と、兵士が詰める櫓、武器を納める蔵としての機能を併せ持っています。

桝形から見た渡櫓(わたりやぐら)。
下に櫓門(やぐらもん)という鉄板張りの大門を有しています。

桝形から見た続櫓(つづきやぐら)。
渡櫓の東に位置し、内部は渡櫓と繋がっています。

内部見学の入り口は、続櫓の南端にあります。
中に入る前に桝形側の石垣を見ると、ここにも刻紋がいくつかありました☆
最近、刻紋を探すのが上手くなった気がします(*^-^*)



中に入ると、桝形側が武者走りという通路、反対側に部屋が縦長に続いています。

↑壁の奥に仕切られた部屋が並んでいます。

こちらは、武者走り側の壁。

床に近い位置には、桝形に向かって鉄砲狭間(てっぽうさま)が。


桝形側についている窓は、重構造になっていました。内側は引違の障子窓。奥は縦格子に突き出し窓。

部屋は、9・9・12・9・15・12畳の6室あります。部屋の内部は入れませんでしたが、それぞれの部屋は漆喰塗りの壁で仕切られていました。

続櫓を北端まで進むと、小階段を上がった先に渡櫓に繋がります。


直ぐ目を奪われたのは、立派な梁や小屋組み。

渡櫓からは、桝形がよく見えます。

渡櫓は4室(公開されているのは内3室)からなっていて、各部屋は梁までの壁で上部は繋がっています。
中央の丁度大門上に当たる部屋が最も床が高くなっています。

門の真上は、櫓落としの仕掛けがあります。


内部の木材は、梁が松、壁に杉、柱に檜が使用されていて、その他にも戸袋や狭間にはケヤキが使用されているようです。

中央の部屋から次の部屋を見ると、かなりの段差があることが分かります。
約60センチほどの段差がありました。
一番奥の部屋は、千貫櫓(せんがんやぐら)に続く渡り廊下に出るのですが、現在渡り廊下の改修中で奥は閉じられていました。
外から見て想像していたよりも内部はとても広くて驚きました☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
大阪城で内部特別公開されている多聞櫓(たもんやぐら)、千貫櫓(せんがんやぐら)、焔硝蔵(えんしょうぐら)に先週末行ってきました。
今回は、多聞櫓(たもんやぐら)をご紹介します☆
公開されているのは、大手口の多聞櫓。
大阪城の4つある出入り口の一つで、表玄関に当たる「大手口」を入り、桝形(ますがた)という防衛のための四角く開けた場所を囲むように建っています。
侵入していた敵を迎え撃つ役割を持った建物です。
他の桝形の場所にもあったのですが、現在は大手口の多聞櫓だけが残っています。
徳川幕府の大阪城再築により建造されましたが、その後落雷で焼失。現在の多聞櫓は幕末に再建され、昭和44年に解体修理されたものです。
多聞とは、石垣の上に建てられた長屋のことで、この大手口多聞櫓は渡櫓と続櫓からなっています。
城壁としての機能と、兵士が詰める櫓、武器を納める蔵としての機能を併せ持っています。
桝形から見た渡櫓(わたりやぐら)。
下に櫓門(やぐらもん)という鉄板張りの大門を有しています。

桝形から見た続櫓(つづきやぐら)。
渡櫓の東に位置し、内部は渡櫓と繋がっています。
内部見学の入り口は、続櫓の南端にあります。
中に入る前に桝形側の石垣を見ると、ここにも刻紋がいくつかありました☆
最近、刻紋を探すのが上手くなった気がします(*^-^*)


中に入ると、桝形側が武者走りという通路、反対側に部屋が縦長に続いています。
↑壁の奥に仕切られた部屋が並んでいます。
こちらは、武者走り側の壁。
床に近い位置には、桝形に向かって鉄砲狭間(てっぽうさま)が。
桝形側についている窓は、重構造になっていました。内側は引違の障子窓。奥は縦格子に突き出し窓。
部屋は、9・9・12・9・15・12畳の6室あります。部屋の内部は入れませんでしたが、それぞれの部屋は漆喰塗りの壁で仕切られていました。
続櫓を北端まで進むと、小階段を上がった先に渡櫓に繋がります。

直ぐ目を奪われたのは、立派な梁や小屋組み。
渡櫓からは、桝形がよく見えます。
渡櫓は4室(公開されているのは内3室)からなっていて、各部屋は梁までの壁で上部は繋がっています。
中央の丁度大門上に当たる部屋が最も床が高くなっています。
門の真上は、櫓落としの仕掛けがあります。
内部の木材は、梁が松、壁に杉、柱に檜が使用されていて、その他にも戸袋や狭間にはケヤキが使用されているようです。
中央の部屋から次の部屋を見ると、かなりの段差があることが分かります。
約60センチほどの段差がありました。
一番奥の部屋は、千貫櫓(せんがんやぐら)に続く渡り廊下に出るのですが、現在渡り廊下の改修中で奥は閉じられていました。
外から見て想像していたよりも内部はとても広くて驚きました☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
2016年02月06日
豊臣時代の大阪城石垣跡発掘現場
こんばんは⭐️
豊臣時代の大阪城石垣発掘現場の一般公開がされるという事で行ってきました( ⁼̴̀꒳⁼̴́ )✧

大阪城天守閣の南東にある金蔵の東側に発掘調査の現場が有ります。
今月2日に発掘されたばかりの櫓の焼失後と思われる痕跡も見られました。
写真そのままだと分かりづらいので、詳しくは後日載せますね⭐️
大阪城では丁度、櫓の内部も公開されていたのでそちらもじっくり見て来ました⭐️
そして、大阪城と所縁のある神社も少し廻ることが出来ました⭐️
色々面白い探訪が出来て大満足です(◍•ᴗ•◍)
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
豊臣時代の大阪城石垣発掘現場の一般公開がされるという事で行ってきました( ⁼̴̀꒳⁼̴́ )✧

大阪城天守閣の南東にある金蔵の東側に発掘調査の現場が有ります。
今月2日に発掘されたばかりの櫓の焼失後と思われる痕跡も見られました。
写真そのままだと分かりづらいので、詳しくは後日載せますね⭐️
大阪城では丁度、櫓の内部も公開されていたのでそちらもじっくり見て来ました⭐️
そして、大阪城と所縁のある神社も少し廻ることが出来ました⭐️
色々面白い探訪が出来て大満足です(◍•ᴗ•◍)
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
2016年02月02日
松江城天守閣―階段の仕掛け他
こんにちは☆
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
今回は松江城内部の天守閣1階~最上階へ。

お城ならではの面白い構造の一つが、階段です。
急勾配で上り下りも一苦労です。
敵兵が攻め込んできた時を想定して、取り外しの出来るように軽い桐材を使用しています。
城内の兵が上階に逃げた後、階段を取り外して上階に引き上げると、敵兵は上がれない、という仕組みです。
更に、1階と4階の床下には階段の開口部を塞ぐための水平引き戸も付けられています。
引き戸を引くと、階段がどこにあるのか分からないようになります。


1階で注目すべきは、40センチ角はあるだろう太い柱。
「包板矧合わせ(つつみいたはぎあわせ)」という柱で、真ん中の芯になる本柱の周りに板をかぶせ、その上を「かすがい」という金具で打ち付けたり、鉄の輪で巻いて太くしています。
太くて頑丈な柱にするための工夫ですね☆
因みに、創建時は、1階にはトイレと人質を閉じ込めておくための「人質蔵」があったそうですが、現在はその名残はありません。
2階・3階の階段の位置も創建時とは異なっているそうです。
藩主が変わるごとに天守内部も改装されていったことを物語っています。

壁が外部にせり出している部分には、石落としが見えます。石垣をよじ登った真上に位置します。
1層と2層の屋根の間を利用しているため、外部からは分かりづらくなっています。
2階には、建物に関係する展示物が沢山ありました。

こちらは、金具。築城当初に使用された瓦留や、午違蝶番などがあります。

鳥衾(とりふすま)という瓦。(写真上と写真下の上部棚)
鬼瓦の上に乗せる瓦で、五三桐の文様は築城当初のもの。
三つ葉葵の文様は、松平藩主の際のものです。

巴瓦(ともえがわら)。(写真の下段)
種類がとても豊富で様々な紋様の巴瓦が使用されていますが、こちらは、築城当初のものと思われる三つ巴紋の巴瓦。

平瓦。
いくつか平瓦の展示があったのですが、この平瓦には築城当時の堀尾家の使用した分銅紋の刻印があります。
この他、元禄に補修が行われた際に補充された瓦に、年代と職人の名前と思われる刻印が残されていました。


こちらは、鬼瓦。
各面がそれぞれ違う顔をしています。どの鬼瓦にも角が無いのが特徴です。


三階には、窓際の板壁に架けられた小さな階段がありました。
以前はその場所に武者隠しがあったとされていますが、現在は屋根に通じているようです。
なぜ屋根に通じているのかははっきりと分かっていません。


4階の西側中央には2つの小部屋が外に突き出した形であります。
向かって左にあるのが(上の写真)が箱便所というお殿様専用のトイレ。
写真では暗くて見づらいのですが、光が差し込んでいる部分が、鉄砲狭間です。
この場所は、大きな破風(はふ)の内側にあり、天守閣内から本丸にいる敵兵に向けての銃撃に最も有効な場所であったと考えられます。
それにしても、トイレから攻撃というのはこの時代でないと考えられないですね( ゚Д゚)

そしていよいよ天守閣の最上階「天狗の間」
四方を見渡すことのできるよう、壁が無い「望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)。
眺めがあまりに良いので、外ばかりを撮って、肝心の内部写真を撮り忘れました。。。
お城ならではの工夫が沢山見られて、とても楽しい探訪でした。
住居にそのままこの仕掛けは使用できませんが、その仕掛けの目的が一貫しているという点には見習うところもある気がします。
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
今回は松江城内部の天守閣1階~最上階へ。
お城ならではの面白い構造の一つが、階段です。
急勾配で上り下りも一苦労です。
敵兵が攻め込んできた時を想定して、取り外しの出来るように軽い桐材を使用しています。
城内の兵が上階に逃げた後、階段を取り外して上階に引き上げると、敵兵は上がれない、という仕組みです。
更に、1階と4階の床下には階段の開口部を塞ぐための水平引き戸も付けられています。
引き戸を引くと、階段がどこにあるのか分からないようになります。
1階で注目すべきは、40センチ角はあるだろう太い柱。
「包板矧合わせ(つつみいたはぎあわせ)」という柱で、真ん中の芯になる本柱の周りに板をかぶせ、その上を「かすがい」という金具で打ち付けたり、鉄の輪で巻いて太くしています。
太くて頑丈な柱にするための工夫ですね☆
因みに、創建時は、1階にはトイレと人質を閉じ込めておくための「人質蔵」があったそうですが、現在はその名残はありません。
2階・3階の階段の位置も創建時とは異なっているそうです。
藩主が変わるごとに天守内部も改装されていったことを物語っています。
壁が外部にせり出している部分には、石落としが見えます。石垣をよじ登った真上に位置します。
1層と2層の屋根の間を利用しているため、外部からは分かりづらくなっています。
2階には、建物に関係する展示物が沢山ありました。
こちらは、金具。築城当初に使用された瓦留や、午違蝶番などがあります。
鳥衾(とりふすま)という瓦。(写真上と写真下の上部棚)
鬼瓦の上に乗せる瓦で、五三桐の文様は築城当初のもの。
三つ葉葵の文様は、松平藩主の際のものです。
巴瓦(ともえがわら)。(写真の下段)
種類がとても豊富で様々な紋様の巴瓦が使用されていますが、こちらは、築城当初のものと思われる三つ巴紋の巴瓦。
平瓦。
いくつか平瓦の展示があったのですが、この平瓦には築城当時の堀尾家の使用した分銅紋の刻印があります。
この他、元禄に補修が行われた際に補充された瓦に、年代と職人の名前と思われる刻印が残されていました。
こちらは、鬼瓦。
各面がそれぞれ違う顔をしています。どの鬼瓦にも角が無いのが特徴です。
三階には、窓際の板壁に架けられた小さな階段がありました。
以前はその場所に武者隠しがあったとされていますが、現在は屋根に通じているようです。
なぜ屋根に通じているのかははっきりと分かっていません。
4階の西側中央には2つの小部屋が外に突き出した形であります。
向かって左にあるのが(上の写真)が箱便所というお殿様専用のトイレ。
写真では暗くて見づらいのですが、光が差し込んでいる部分が、鉄砲狭間です。
この場所は、大きな破風(はふ)の内側にあり、天守閣内から本丸にいる敵兵に向けての銃撃に最も有効な場所であったと考えられます。
それにしても、トイレから攻撃というのはこの時代でないと考えられないですね( ゚Д゚)
そしていよいよ天守閣の最上階「天狗の間」
四方を見渡すことのできるよう、壁が無い「望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)。
眺めがあまりに良いので、外ばかりを撮って、肝心の内部写真を撮り忘れました。。。
お城ならではの工夫が沢山見られて、とても楽しい探訪でした。
住居にそのままこの仕掛けは使用できませんが、その仕掛けの目的が一貫しているという点には見習うところもある気がします。
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
2016年02月01日
松江城の構造と付櫓(つけやぐら)
こんにちは☆
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
松江城の本丸へ☆今回は天候が優れなかったので、写真がイマイチ(+_+)

ですので、以前訪れた際の写真を☆
天守閣のみを撮った写真が無かったため、お姫様の衣装で記念撮影してもらった時のものです(/ω\)

松江城は、5層6階の「望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)」。織田信長が建てた安土城や豊臣秀吉時代の大阪城と同じタイプです。
全国に残っている城の中でも唯一安土城の形式を引き継いでいる天守閣で、面積では姫路城に次いで第二位という貴重なお城です。
望楼型という天守の構造は、上下層が一体型ではない構造です。
主に居館部分となる下層部の入母屋屋根の上に、物見櫓が載せられたものが望楼型天守の始まり。 望楼部は基本的に、下層部の梁の上に載る形で造られています。
また大きな入母屋部分は屋根裏部屋となっており、外観の層と内部の階数が一致しないことが多いのも特徴です。
松江城は、全体で3段重ねの建物。
石垣内部には地下一階があり、その上の1段目には2階建て建物、その上の2段目には大きな入母屋屋根、更に上の3段目には白い漆喰の塗り壁の2階建ての望楼(ぼうろう)という物見櫓(ものみやぐら)を載せています。
正面入り口には付櫓(つけやぐら)がくっついています。
付櫓に入る鉄扉(くろがね)の左側石垣に、鍵の形をした刻印があるはずなのですが、見つけられませんでした( ;∀;)残念・・・
1段目や付櫓の黒い壁部分は、すすと柿の渋を混ぜた墨を塗った板を土壁の外に張ってあります。


付櫓には、左右に「石落とし」。
壁を外側に少し張り出し30センチほどの隙間を造り、そこから石を落としたり、鉄砲や矢を放つための仕掛けです。
石落としの横には、武者格子窓(むしゃごうしまど)。

こちらは、内部から撮った武者格子窓です。
格子に使われる木材の断面が菱形になっているのが特徴です。
これは、鉄砲を撃つときに銃身を斜めに向けたりと広い角度で撃つことが出来るように、また鉄砲を撃った際の煙を外に出す為の工夫です。

こちらは、付櫓の内部の様子です。
石落とし、武者格子の下に見える四角い窓のようなものは、「狭間(さま)」。銃を発射するための穴です。
付櫓だけで14の狭間があります。
城ならではの建物の工夫が沢山!
次回は、1階から上層階に進みます☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
松江城の本丸へ☆今回は天候が優れなかったので、写真がイマイチ(+_+)
ですので、以前訪れた際の写真を☆
天守閣のみを撮った写真が無かったため、お姫様の衣装で記念撮影してもらった時のものです(/ω\)
松江城は、5層6階の「望楼型天守(ぼうろうがたてんしゅ)」。織田信長が建てた安土城や豊臣秀吉時代の大阪城と同じタイプです。
全国に残っている城の中でも唯一安土城の形式を引き継いでいる天守閣で、面積では姫路城に次いで第二位という貴重なお城です。
望楼型という天守の構造は、上下層が一体型ではない構造です。
主に居館部分となる下層部の入母屋屋根の上に、物見櫓が載せられたものが望楼型天守の始まり。 望楼部は基本的に、下層部の梁の上に載る形で造られています。
また大きな入母屋部分は屋根裏部屋となっており、外観の層と内部の階数が一致しないことが多いのも特徴です。
松江城は、全体で3段重ねの建物。
石垣内部には地下一階があり、その上の1段目には2階建て建物、その上の2段目には大きな入母屋屋根、更に上の3段目には白い漆喰の塗り壁の2階建ての望楼(ぼうろう)という物見櫓(ものみやぐら)を載せています。
正面入り口には付櫓(つけやぐら)がくっついています。
付櫓に入る鉄扉(くろがね)の左側石垣に、鍵の形をした刻印があるはずなのですが、見つけられませんでした( ;∀;)残念・・・
1段目や付櫓の黒い壁部分は、すすと柿の渋を混ぜた墨を塗った板を土壁の外に張ってあります。
付櫓には、左右に「石落とし」。
壁を外側に少し張り出し30センチほどの隙間を造り、そこから石を落としたり、鉄砲や矢を放つための仕掛けです。
石落としの横には、武者格子窓(むしゃごうしまど)。
こちらは、内部から撮った武者格子窓です。
格子に使われる木材の断面が菱形になっているのが特徴です。
これは、鉄砲を撃つときに銃身を斜めに向けたりと広い角度で撃つことが出来るように、また鉄砲を撃った際の煙を外に出す為の工夫です。
こちらは、付櫓の内部の様子です。
石落とし、武者格子の下に見える四角い窓のようなものは、「狭間(さま)」。銃を発射するための穴です。
付櫓だけで14の狭間があります。
城ならではの建物の工夫が沢山!
次回は、1階から上層階に進みます☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
2016年01月29日
松江城の石垣と刻紋探し
こんにちは☆
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
今回は、松江城の石垣


場所に応じて、野面積(のずらづみ)、打込接(うちこみはぎ)、切込接(きりこみはぎ)が使い分けられています☆
野面積は、自然石をそのまま積み上げていく方法。
打込接は、槌(つち)で叩いて整形した割石を使用し、隙間を間詰石(まづめいし)で埋めて積み上げる方法。
切込接は、大きさ、形が一定に整形された切石(きりいし)を用いて、それぞれの石の切り口を合わせて積み上げる方法。
松江城の石垣では、打込接が最も多いようでした。 急な勾配を造るのに、切込接には劣りますが野面積よりも適しているという特徴があります。
そして、以前名古屋城に行った知り合いから送ってもらった写真で知った、城の石垣に掘られた刻紋。
松江城にもあるか探してみたところ、ありました(*^-^*)
↓は、松江城の初代藩主堀江家の家紋で「分銅紋(ぶんどうもん)」

この分銅紋は、火点(かてん)という本坂を駆け上がってきた敵軍を迎え撃つ際に重要な場所である石垣に多く見られました。
登城する家来たちの目に必ず家紋が目に入るように選んで造られたと考えられるそうです。
その他にも、様々な刻紋が見られました。

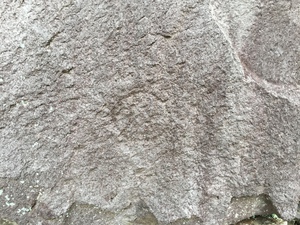

私は見つけられなかったのですが、彫刻ではなく墨で描かれたものも残っているそうです。
はっきり写真に写らないものもあったので、ほんの一部ですが、様々な紋様があって刻紋探しだけでも十分に楽しめます☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
今回は、松江城の石垣
場所に応じて、野面積(のずらづみ)、打込接(うちこみはぎ)、切込接(きりこみはぎ)が使い分けられています☆
野面積は、自然石をそのまま積み上げていく方法。
打込接は、槌(つち)で叩いて整形した割石を使用し、隙間を間詰石(まづめいし)で埋めて積み上げる方法。
切込接は、大きさ、形が一定に整形された切石(きりいし)を用いて、それぞれの石の切り口を合わせて積み上げる方法。
松江城の石垣では、打込接が最も多いようでした。 急な勾配を造るのに、切込接には劣りますが野面積よりも適しているという特徴があります。
そして、以前名古屋城に行った知り合いから送ってもらった写真で知った、城の石垣に掘られた刻紋。
松江城にもあるか探してみたところ、ありました(*^-^*)
↓は、松江城の初代藩主堀江家の家紋で「分銅紋(ぶんどうもん)」

この分銅紋は、火点(かてん)という本坂を駆け上がってきた敵軍を迎え撃つ際に重要な場所である石垣に多く見られました。
登城する家来たちの目に必ず家紋が目に入るように選んで造られたと考えられるそうです。
その他にも、様々な刻紋が見られました。
私は見つけられなかったのですが、彫刻ではなく墨で描かれたものも残っているそうです。
はっきり写真に写らないものもあったので、ほんの一部ですが、様々な紋様があって刻紋探しだけでも十分に楽しめます☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
2015年12月04日
名古屋城の石垣と刻紋
こんにちは☆
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
先日名古屋城に行かれた方が石垣の写真を送ってくれました(^^)

石垣に様々な文様が刻印されています。
石垣の文様といえば、「鬼門にあたる方角の角に刻印される魔よけ」と思っていたのですが、送っていただいた写真はどれも角ではなく、
ムムムっつ?!(+_+)と思っていたら、
これは、石垣を作る際の所有者(藩)の印だそうです。 全くもって知りませんでした( ;∀;)
何でも、石垣工事は天下普請の助役大名に分担させて行ったそうです。
工事現場はごった返し、複雑な分担と他家との競争もあり、それぞれ各地から苦労して取り寄せた大切な石材を紛失したり盗まれるのを防ぐために紋を付けて所有者を明確にする必要があったのだとか。


刻印(刻紋)には、□や○や△などを組み合わせたり数字を記入したりととても種類が豊富なようです。
因みに名古屋城の土台となる石垣に使われた石の総数は10万個から20万個。それらの石の中には讃岐地方から集められました石もあるのだそうです。
名古屋城の石垣、ぜひ実際に行って沢山の刻紋を見てみたくなりました☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp
さぬき市の「古民家再生と築40年以上の木造専門」の
工事も頼める設計屋さん
谷野設計の学芸員・谷野友香です(^^)
お読みいただき、有難うございます。
先日名古屋城に行かれた方が石垣の写真を送ってくれました(^^)
石垣に様々な文様が刻印されています。
石垣の文様といえば、「鬼門にあたる方角の角に刻印される魔よけ」と思っていたのですが、送っていただいた写真はどれも角ではなく、
ムムムっつ?!(+_+)と思っていたら、
これは、石垣を作る際の所有者(藩)の印だそうです。 全くもって知りませんでした( ;∀;)
何でも、石垣工事は天下普請の助役大名に分担させて行ったそうです。
工事現場はごった返し、複雑な分担と他家との競争もあり、それぞれ各地から苦労して取り寄せた大切な石材を紛失したり盗まれるのを防ぐために紋を付けて所有者を明確にする必要があったのだとか。
刻印(刻紋)には、□や○や△などを組み合わせたり数字を記入したりととても種類が豊富なようです。
因みに名古屋城の土台となる石垣に使われた石の総数は10万個から20万個。それらの石の中には讃岐地方から集められました石もあるのだそうです。
名古屋城の石垣、ぜひ実際に行って沢山の刻紋を見てみたくなりました☆
************************
古民家再生と築40年以上の木造住宅改修・設計専門店
工事も頼める設計屋さん
㈲谷野設計
さぬき市大川町富田西2911-1
0879-43-6807
info@tanino-sekkei.co.jp





